
「立木が成長しすぎて邪魔になってしまった」「所有している山林をきれいにしたい」といった理由で、木の伐採を検討している方もいるのではないでしょうか。
しかし、この伐採作業、じつは“森林法”という法律で厳しく管理がされており、きちんと行政手続きを踏んでからおこなわないと、法律違反となってしまうことがあるのです。
そこで今回は、森林で伐採をおこなうときの手続きについて、その内容や届出の提出方法などを解説します。保有している山林の伐採を検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
森林での伐採には「伐採届」が必要なこともある

「自分の土地にある木であれば、自由に伐採しても構わないだろう」と思っている方もいるかもしれません。しかし、じつは森林を伐採するためには管轄の市町村や都道府県などから“許可”を得なければならないことがあるのです。
ここではまず、どういう場合に伐採許可が必要となるのか、許可を得るためにはどのような届出をすればよいのか、などについてご紹介しましょう。
どういう場合に伐採の許可が必要?
個人が勝手に木の伐採をおこなってしまうと、二酸化炭素の吸収や酸素の放出などに必要となる大切な森林が、どんどん減ってしまいますよね。こうしたことを防ぐため、日本では各都道府県ごとに、保護すべき森林区域が定められています。これが、“地域森林計画”と呼ばれるものです。
都道府県が制定した“地域森林計画”の区域内にある森林を伐採する場合、たとえたった1本の伐採であろうと、行政からの許可が必要となります。ただし、以下に該当する場合は伐採許可が必要ありません。
- 地域森林計画の対象区域外の木を伐採するとき
- 例外的に伐採が認められている木を伐採するとき(※)
(※倒れそうな木や枯れた木を伐採する場合、法令に基づく測量や実地調査、施設保守の支障となる木を伐採する場合 など)
上記以外の森林伐採は、基本的にすべて行政からの許可が必要であると考えておきましょう。
「伐採届」とは
伐採の許可を得るためには、木の伐採をおこなう前に“伐採届”を提出する必要があります。具体的な提出物や提出時期、提出先は以下のとおりです。
<提出物>
・伐採および伐採後の造林の届出書(伐採届)
伐採することや、その後に造林(ぞうりん/新たに木を植えること)をおこなうことについて、許可を得るための書面です。
<提出時期>
伐採作業日の90日前~30日前まで
<提出先>
伐採対象の森林を管轄とする市町村長
※伐採面積が広範囲となる場合、地域によっては都道府県知事に提出しなければならないこともあります。
なお伐採届の提出を怠った場合、森林法に基づき罰金が科されるおそれもあります。伐採作業は、伐採届の提出が済んでいるかどうかをしっかり確認してからおこないましょう。
「保安林」の場合は、別の許可が必要!
伐採しようとしている立木が、農林水産大臣や都道府県などから“保安林”として指定されている場合、通常の伐採届では伐採許可を得ることができません。保安林として指定されている森林は、伐採に厳しい制限が設けられているからです。
保安林の伐採をおこないたい場合は、市町村長に提出する通常の伐採届ではなく、都道府県知事宛ての特別な伐採届(保安林内立木伐採許可申請書など)で許可を申請することになります。
通常の伐採届とは手続き方法が異なりますので、伐採をおこなう際は、その木が保安林に指定されているかどうかを事前に確認しておきましょう。
森林で伐採を始める前にしておくこと

ここからは、実際に森林で伐採をおこなう際に必要な手続きの流れをご紹介します。手続きが漏れてしまうと森林法違反になってしまうこともあるため、気をつけましょう。
<1>伐採届が必要かどうかを確認する
まずは伐採を検討している森林が、地域森林計画の対象区域内にある森林であるかどうかを確認してください。地域森林計画の対象森林であったとしても、倒木の危険性があるケースなど、例外的に届出が必要ない場合もあります。判断が難しい場合は、最寄りの市町村窓口に確認しましょう。
<2>必要な書類をそろえる
伐採届が必要であることがわかったら、必要な書面をそろえます。行政のホームページ上などにある伐採届のフォーマットを印刷し、必要事項を記入しましょう。なお市町村によっては、伐採場所がわかるような図面や登記事項証明書のコピーなどの提出が求められることもあります。事前に市町村窓口に連絡し、必要となる書面を確認しておくと安心です。
<3>期日まで伐採届を市町村窓口に提出する
伐採届は、伐採作業日の90日前から提出することができます。伐採作業日の30日前が期日となりますので、遅れることのないよう、余裕を持って提出しましょう。
伐採届を提出して伐採したあとには「状況報告書」も必要

地域森林計画区域内で伐採をおこなった場合、伐採後に“状況報告書”と呼ばれる書類を提出しなければなりません。こちらの書面も伐採届と同様に、提出が漏れると森林法違反となり多額の罰金が科せられるおそれがあるので注意しましょう。状況報告書の具体的な提出物や提出時期、提出先は以下のとおりです。
<提出物>
・伐採および伐採後の造林にかかる森林の状況報告書
伐採方法や伐採にかかった期間、造林の方法などについて報告するための書面です。伐採前後の森林の様子を写した写真の添付が必要となる場合もあります。
<提出時期>
造林作業終了日の30日後まで(造林しない場合は伐採終了日の30日後まで)
<提出先>
伐採対象の森林を管轄とする市町村長
※伐採面積が広範囲となる場合、地域によっては都道府県知事に提出しなければならないこともあります。
伐採届の必要な森林での伐採なら業者に依頼するのがおすすめ!

地域森林計画区域に入っている森林の伐採をおこなう場合は、ここまでご紹介してきたとおり、伐採届や状況報告書の提出など、複雑な行政手続きが必要となります。はじめて伐採をおこなう方の場合、「手続きが漏れたらどうしよう」「書面の記載方法がわからない」と悩んでしまうこともあるでしょう。
そういった場合は、伐採を業者に依頼するのがおすすめです。伐採業者の多くは伐採届に関する知識も豊富ですので、伐採届の書き方や提出すべき書類の集め方などについて、親身に相談に乗ってくれるでしょう。
弊社にご相談いただければ、実績豊富な伐採業者を迅速にご紹介することが可能です。もちろんご紹介料は無料ですので、安心してお問い合わせください。
まとめ
今回は、伐採の際に必要となる“伐採届”や、伐採後に提出する“状況報告書”についてご紹介しました。「自分が所有している森林の伐採にも許可が必要だとは、知らなかった」という方もいるのではないでしょうか?
知らなかったでは済まされないのが法律の怖いところです。万が一にでも森林法違反に抵触してしまうことのないように、ぜひ森林伐採をおこなう際はプロの伐採業者に相談してみてください。
スムーズな伐採作業をおこなってくれるのはもちろんのこと、必要書面などについても、きっと丁寧なアドバイスがもらえるはずです。

もみの木は、古くからクリスマスツリーとして多くの方に親しまれてきました。そんなもみの木は、健やかに育っていくと、高さ30m近くまで成長するといわれています。
そのため、伐採する必要が発生したときには、可能であれば伐採業者に依頼したほうがよいです。自分で伐採することも可能ですが、大木に育ってしまっている場合は高所での作業になるため、作業が非常にむずかしくなり、危険がともなうからです。
本コラムでは、もみの木の伐採を自分でおこなう方法や優良業者の選び方、伐採の後始末の方法などをご紹介していきます。コラムを最後まで読んで、自分で伐採できる基準を見極めて、もしできないと感じたら業者に依頼してみるとよいです。
もみの木の伐採を自分でやる場合
ここでは、もみの木の伐採を自分でおこなう場合の方法についてご紹介していきます。伐採に必要となる道具や伐採の手順についてご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
自分で伐採できる基準

伐採を自分でおこなう場合、ある程度慣れていないとむずかしいでしょう。伐採の経験がない素人の方がおこなう際は、高さが3m未満、幹の直径が20cm以下の庭木であれば、無理をすることなく伐採することができるとされています。
伐採の準備
伐採をする際は、まず枝の除去をおこないます。あらかじめ枝を切っておかないと、木が倒れたときに枝が折れて周りに飛び散ってしまうことがあり、非常に危険です。そして、実際に伐採をおこなう際は、以下のような道具が必要になります。ひとつずつ確認して、必ず手元に準備しておきましょう。
・チェーンソー
チェーンソーは、伐採をおこなううえで欠かせない道具になります。チェーンソーはサイズや動作方式などさまざまなものがあるため、庭木の大きさに合わせて、使い勝手のよいものを選びましょう。
・ノコギリ
ノコギリも伐採をするうえで必要な道具になります。ノコギリはチェーンソーに比べると、木を切り倒すのに時間がかかりますが、正確に木を倒すことができます。そのため、木を切る道具としてひとつは持っておくと重宝するでしょう。
・ロープ
ロープは木を倒す方向を定めるために使用します。庭木の上の位置にロープをくくり付けて、目的とする方向に引っ張ることで、木を倒したい方向に倒すことができます。
・クサビ
クサビは、固い木材や金属で作られたV字型の形をしている道具です。チェーンソーで切り込んだ切り口にクサビを差し込み、ハンマーなどで強くたたくことで、木が倒れる方向を調整することができます。
・シャベル
シャベルは、伐採が終わった後に残った切り株を撤去するために使用します。切り株の根っこにかぶさっている土を掘るために使います。具体的な切り株の撤去方法については後述していますので、参考にしてみてください。
伐採方法
伐採に必要な道具を準備し終えたら、実際に作業をはじめていきましょう。具体的なもみの木の伐採手順は以下のとおりです。
1.もみの木を倒す方向を決める
はじめに、もみの木を倒す方向を決めておく必要があります。とくに計画を立てずに木を伐採してしまうと、予想しない方向に木が倒れてしまい、非常に危険です。
2.受け口を作る
木を倒す方向を決めたら、実際に木を切っていきます。まずチェーンソーを使用して、木を倒す方向に「受け口」と呼ばれる切り込みを入れていきます。受け口は、ひざ下くらいの位置から、真っすぐな切り込みを入れましょう。そして、斜め上から、直線の切り込みに向かって切っていきます。横から切り口を見たとき、三角形の形になっていれば大丈夫です。
3.追い口を作る
受け口ができたら、その反対側に「追い口」と呼ばれる切り込みを入れていきます。追い口は、受け口の斜めに入っている切り込みに向かって、チェーンソーを入れるとよいです。木の幹の中心あたりまで切り込みを入れたら完成です。
4.もみの木を倒す
受け口と追い口を作ることができたら、いよいよもみの木を倒していきます。追い口にクサビを打ち込み、ハンマーなどを使って強くたたき込みましょう。すると少しずつ木が傾いてきます。木が倒れそうになったら、クサビで倒れる方向を微調整して、慎重に伐採をしていきましょう。木が倒れるときは、すぐに安全な場所に移動するとよいです。
5.倒したもみの木を処分する
もみの木を伐採し終えたら、きちんと木は処分するようにしましょう。木の処分方法については後述いたします。
危険な場合は業者に依頼
もみの木は大きく成長する庭木なので、伐採に慣れていない方にとっては、非常に危険がともなうものです。とくにチェーンソーを使用する場合は、使用経験がある方に手伝ってもらうと、より安全に作業できます。しかし、自分では伐採ができないと判断した場合は、伐採業者に依頼してみることをおすすめします。
弊社は、日本全国にあるさまざまな業者と連携しており、ご要望に合った業者をご紹介しています。24時間365日いつでも電話対応をおこなっておりますので、もみの木の伐採に関して悩みごとがある場合は、まずは一度お電話ください。伐採のプロが迅速に対応させていただきます。
もみの木の伐採を業者に依頼した場合の費用
これまで、自分でもみの木を伐採する方法についてみてきました。ここからは、伐採を業者に依頼する場合の費用や、優良な業者の選び方についてご紹介していきます。
もみの木が大きいほど費用は高くなる

伐採を業者に依頼すると、もみの木が大きくなるほど、費用も高くなっていきます。具体的には、「地面から先端までの高さ」「木の幹の太さ」「作業のむずかしさ」を考慮したうえで、伐採の料金は算出されます。
たとえば、周りに立木が密集していたり、障害となる建物や電柱などがあったりする場合は、作業難易度が上がるため、そのぶん料金が高くなってしまうことがあるでしょう。伐採費用の目安としては、庭木1本あたり2,000円からとなっております。
正確な伐採費用を知る方法
正確な伐採費用を知るためには、業者から事前に見積り金額を出してもらうとよいです。見積りをとることで、「どのような作業をするのか」「注意事項はあるのか」などを知ることができます。
また、複数の業者から見積りをとる相見積りをおこなうことで、より格安でサービスがよい業者を選ぶことができるでしょう。そのため、はじめから1社だけに絞らずに、複数の業者の料金やサービス内容を見比べてみることで、よりよい業者に巡り合えるはずです。
伐採業者の選び方
よりよい伐採業者を選ぶには、下記のような点に注目するとよいでしょう。ひとつずつ確認していきましょう。
・料金明細がはっきりしているか
業者の見積りをおこなったときに、伐採にかかる料金だけでなく、何にいくらかかるのかを把握しておくことが重要です。金額だけしか記載されていないと、後から追加料金を請求されてしまうこともあるでしょう。そのため、見積りの際には、料金明細がはっきりしているか、事前にきちんと確認しておきましょう。
・庭木1本単位でも対応してくれるか
庭木を1本からでも伐採をしてくれるのかを確認しておくことも重要です。1本だけの伐採というのは、出張費や人件費のコストがかかり、割に合わないと感じる業者も多いでしょう。しかし、「庭木1本から伐採可能」という宣伝文句を気に入ってもらうことで、次のサービスにつなげている優良業者もあります。
・ホームページがわかりやすく作られているか
会社のホームページがきちんと作られていると、信頼できる業者である確率が高いです。伐採の実績や料金体系、サービス内容などが明確に記載されているか確認しましょう。また、お客様の口コミも参考にするとよいです。とくに、よい口コミと悪い口コミを載せている会社は、お客様満足度の向上に努めている可能性が高いです。
・業者の規模だけで決めない
大手の業者に依頼するのか、地元の業者に依頼するのか、迷う方もいるでしょう。大手の業者に依頼するメリットは、大きな資本力にあります。充実した資本力によって、迅速な対応をおこなってくれる会社が多いでしょう。
一方、地元密着型の業者は、値段交渉に応じてくれたり、気軽にコミュニケーションをとったりすることができるでしょう。そのため、会社の規模にとらわれず、料金やサービス内容などをきちんと考慮したうえで、業者を選択するとよいです。
このように、優良な業者を選ぶには、まずは複数の業者から見積りをとってみることをおすすめします。弊社では、全国のさまざまな業者と連携しているため、ご要望にマッチした業者をご紹介しています。相見積りにも対応することが可能です。もみの木の伐採にお悩みの方は、ぜひお電話ください。
もみの木の伐採だけで終わりじゃない!後始末の方法
もみの木を伐採し終えた後は、きちんと後始末をしなければなりません。ここからは、具体的な後始末の方法をご紹介していきます。
伐採した幹の処分法は主に3つ

伐採した幹の処分には、以下のような3つの方法が挙げられます。伐採した後は、そのまま放置することなく、適切に処分するようにしましょう。
・燃えるゴミに出す
伐採した木は燃えるゴミとして出すことができます。ゴミとして出す際は、細かく切ってゴミ袋に入る大きさにしましょう。自治体によっては、伐採した木は粗大ゴミ扱いになることもあるため、事前に市や自治体の窓口などで確認しておくようにしましょう。
・クリーンセンターに持っておく
伐採したもみの木の量が多く、ゴミ袋に入りきらない場合は、クリーンセンターに持っていくとよいでしょう。クリーンセンターとは、市や自治体が管理・運営しているゴミ処理施設のことをいいます。クリーンセンターによっては、ゴミの重量によっては手数料が必要になってくることがあるため、事前にホームページなどで確認しておくようにしましょう。
・業者に引き取ってもらう
伐採したもみの木が多く、自分では処分しきれないと感じた場合は、業者に引き取り依頼をするとよいです。引き取りの費用は、木の幹の直径や枝の長さなどによって変わってきます。業者によってサービス内容がさまざまなので、自分に適した業者を選ぶとよいでしょう。
切り株を撤去する方法
庭木を伐採した後に残った、木の根の部分を切り株といいます。切り株を撤去するには、以下のような道具を準備して、適切な手順を踏むことでおこなうことができます。
〇用意する道具
- シャベル、スコップ
- 電動ハツリ機(ノコギリやチェーンソーでも可能)
- ブルーシート
〇手順
- ブルーシートを切り株の近くに敷く
- 切り株の根っこをシャベルやスコップで掘り起こす(掘り起こした土はブルーシートの上に乗せる)
- 根っこが見えてきたら、電動のハツリ機で切断する
- 切断することができたら、切り株を撤去する
- ブルーシートにある土を元の位置に埋め戻して作業完了
全部やってくれる業者もある
業者に伐採を依頼すると、後始末まですべてやってくれる場合もあります。しかし、業者によっては、伐採と後始末は別料金になっていることもあるでしょう。そのため、複数の業者から相見積りをとって、料金体系をきちんと把握しておくことが重要です。
弊社では、24時間365日いつでも電話対応をおこなっております。全国各地の業者からお客様にマッチした業者をご紹介しています。いくつかの業者から見積りをとって検討することで、優良な業者に出会えることでしょう。まずは一度、お気軽にお電話ください。プロがあなたのお悩みを解決してくれるはずです。

シュロはヤシの木に似た見た目をしており、どことなく南国の雰囲気を感じることができる樹木です。その南国風の見た目に反して比較的寒さには強く、東北や北海道でも育つことができ、日本の広い範囲で見ることができます。
お手軽に南国の雰囲気を楽しめるシュロですが、時間をかけて高木へと成長していくためお庭で育てる場合は注意が必要です。お庭のシュロがあまりに大きくなりすぎると、強風が吹いた際に倒れたり、電線に枝葉が接触したりするおそれがあります。そのため、場合によってはシュロを伐採する必要がでてくるかもしれません。
しかし、シュロの伐採はひと筋縄ではいかないのはご存じでしょうか。このコラムでは、シュロの伐採が難しい理由や伐採に適した方法などをご紹介していきます。
シュロの伐採に意外と難儀する理由
シュロは、プロでも伐採が難しいことがある樹木です。ここでは、そんなシュロの伐採が難しい理由をいくつかご紹介していきます。
幹の皮むきをしなければ伐採しにくい

大きく成長した樹木を伐採するとなると、チェーンソーを使うことを検討する方も多いと思います。実際に、大きな樹木を効率よく伐採するためにチェーンソーは必要不可欠です。
しかし、シュロは幹の周りが繊維状の皮で覆われているため、チェーンソーで伐採することが非常に難しいのです。仮に皮をむかずにチェーンソーで伐採しようとすると、繊維がからまって故障してしまいかねません。
繊維や幹が丈夫な性質を持つ
シュロを覆う繊維状の皮は、とても丈夫で皮をむくのもひと苦労です。さらに、皮の下にはとても固い幹があるため、皮をむけたとしても切断するのは難しいです。このことから、シュロの伐採はかなりの重労働になるといえます。
時間が経てば高木へ生長する
シュロの成長速度は決して早くはありませんが、時間をかけてじっくりと高木へ成長していきます。個体差はありますが5m以上に成長するケースもあり、伐採が困難になりやすいです。
重心が高く、倒れる方向のコントロールが難しい
木を伐採して安全に倒すためには、木を倒す方向へしっかりとコントロールする必要があります。しかし、重心が高い木は伐採時に倒れる方向をコントロールしづらいです。そのため、高く成長するうえに枝葉が上部にまとまって成長する関係上、重心が高くなりやすいシュロは安全に伐採をおこなうのが難しいです。
ご紹介してきたとおり、シュロは伐採が難しい樹木です。そのため、シュロの伐採は、なるべく業者に依頼することをおすすめします。弊社では、伐採のプロをご紹介しているため、お庭のシュロが大きくなりすぎてお困りの際はご相談してください。
シュロを伐採するには「斧」が最適!
シュロの伐採は危険がともなうため、可能な限り業者に依頼することをおすすめします。しかし、中には自分で伐採をしてみたいというかたもいるのではないでしょうか。ここではシュロを伐採する際のアドバイスをご紹介していきます。自分でシュロを伐採してみたいという方は参考にしてみてください。
斧なら繊維ごと切ることができる

シュロは繊維状の皮で覆われている関係上、チェーンソーで伐採することができません。また、庭木の伐採でよく使われるノコギリも繊維状の皮に刃が引っかかってしまうため、シュロの伐採に使うのは難しいです。
そこで活躍するのが斧です。斧であれば刃が繊維状の皮に引っかかってしまうことがないため、皮ごとシュロを伐採することができます。しかし、斧での伐採はかなりの重労働になる点は留意しておきましょう。
皮をむけばチェーンソーも使える
お話したとおり、斧でシュロを伐採するのはかなりの体力と力を求められる重労働です。そのため、なんとかしてチェーンソーでシュロを伐採できないかと思う方もいるのではないでしょうか。
シュロをチェーンソーで伐採できないのは、繊維状の皮がからまってしまうのが理由なので、この皮をむけばチェーンソーを使うことも可能です。シュロの皮は、ナタなどで切れ込みを入れるとむきやすくなります。
倒れると危険!少しずつ切っていこう
シュロは重心の高くなりやすい樹木なので、一度にたくさん幹を切り進めると思わないタイミングで木が倒れてしまうおそれがあります。予期しないタイミングでの倒木はケガの元であるため、伐採をおこなう際は少しずつ切り進めていくようにしましょう。
狭い庭でのシュロ伐採は難しい!
シュロは倒す方向をコントロールするのが難しいうえに背が高いため、狭い庭で伐採するとなると家へ向かって倒木してしまうおそれもあり、大変危険です。シュロを安全に伐採する自信がないという方は、無理をせずに業者に伐採を依頼しましょう。
弊社では狭い庭でもシュロの伐採をおこなえる、伐採のプロをご紹介しています。安全にシュロの伐採をおこなえる業者をお探しの場合は、通話無料の相談窓口よりご相談ください。
伐採したシュロの処分と活用方法
伐採したシュロは、その後処分をおこなわなければなりません。ここでは、シュロの処分と活用方法についてご紹介します。伐採後のシュロを処分する際の参考にしてみてください。
自治体のゴミ出しルールを確認しよう

伐採したシュロは自治体によっても異なりますが、多くの場合は燃えるゴミとして出すことができます。しかし、伐採したシュロをそのままの状態でゴミに出すことはできません。ゴミとして出すためには、ゴミ袋に入る大きさに細かく切り刻む必要があります。
また、シュロの大きさが一定以上になると燃えるゴミではなく粗大ゴミ扱いになったり、ゴミとして引き取ってもらえなくなったりするので、あらかじめ自治体のホームページなどを確認しましょう。
幹を細かくするなら早めに作業を
水分をたくさん含んでいるシュロですが、伐採後は徐々に切り口から水分が流出して乾燥していきます。樹木は基本的に乾燥するとより強度が増すという性質があり、シュロも例外ではありません。時間が経過するほど、ただでさえ固くて切断が難しいシュロの幹が、乾燥でより切りづらくなってしまいます。そのため、シュロの伐採後は早めに幹を細かく切り刻みましょう。
ほうきやたわしに加工する方法も
シュロの皮の繊維は、柔軟性と耐水性に優れています。そのため、繊維を束ねてほうきやたわしにして利用されるケースがあります。
シュロの繊維で作ったほうきは柔らかいため、床を傷つけずに掃除をすることが可能です。また、シュロのたわしは繊維が細かく洗い物の汚れをしっかり落とすことができます。
シュロ製のほうきやたわしは、掃除用品販売店で取り扱われることがあるほど品質がよいとされているため、気になった方は伐採後のシュロの皮を自分で加工してみてはいかがでしょうか。
処分に困りそうなら伐採と同時に依頼
シュロは、そのサイズと強度から処分が困難な樹木です。あまりにサイズが大きすぎると自分で処分することができず、業者に処分を依頼するしかないというケースもあるかもしれません。
そのため、伐採前に処分のことまでしっかり考えておき、処分に困りそうだと感じた場合は伐採とあわせて業者に依頼してしまうことをおすすめします。弊社では、シュロの伐採や処分、伐根などができる業者をご紹介しています。「シュロが大きくなりすぎてどうにかしたい」という場合はぜひご相談ください。

庭に生えている木を抜根したいと思っても、自力でやろうとするとなかなかの根気と労力がかかります。理由は、木の根は思っている以上に地中に広がっていることが多いためです。
慣れない作業で想像以上に疲れてしまったり、ケガをしてしまったりすることもあります。そのため自分で作業をおこなう前には、抜根の手順など最低限のことを知っておくとよいでしょう。
そこでこの記事では、抜根の手順や注意点についてご紹介します。抜根を業者に依頼したときの費用相場についてもまとめてみました。抜根が自力でできるのかどうかをしっかりご判断するためにも、参考にしてください。
抜根を自力でやるなら「根気」が必要
抜根とは、木を根ごと抜きとる作業をいいます。抜根を自力でおこなうのは大変といわれていますが、その理由についてご説明します。
抜根に根気が必要なのはなぜ

大きく成長している木ほど抜根作業は大変だと思われる方も多いのではないでしょうか。しかし幹が細い木でも、根は深く広く生えていることがあります。地中の四方八方に広がっている根を掘り起こし少しずつ取り除いていかなければなりません。単純ですがとても根気のいる作業となり、時間や労力がかかります。
抜根だけではなく、抜根のあとには根の処分もしなければなりません。そのまま放置しておくと、シロアリの住処になるおそれがあるためです。業者によっては、抜根を依頼すると処分までしてくれる業者もあります。自分で処分するのが面倒な場合はそのような業者に依頼し、抜根から処分まで任せるとよいでしょう。抜根を自力でおこないたい方のために、抜根手順や処分方法ものちほどご紹介します。
業者に依頼するメリットや費用について
抜根を自力でおこなうことが大変そうだと思った場合は、業者に依頼するとよいでしょう。四方八方に広がった根をすべて自分で取り除くには、かなりの時間と労力がかかります。業者に依頼すれば、時間や労力をかけることなく抜根してもらうことができます。
抜根を業者に依頼したときの費用相場は、幹の太さが15センチメートル~30センチメートルの場合は3,000円~5,000円ほどとなります。31センチメートル~50センチメートルの場合は7,000円~20,000円ほどが相場となり、対象となる木の種類や幹の太さ、抜根をする場所の状況によって金額が異なります。
また業者によっては、抜根のみをおこなうのか、そのあとの処分なども含まれているかなど作業内容も異なります。幹の太さによっては重機を使う場合もあり、その場合は別途費用が発生することもあります。依頼する前には無料見積りや現地調査を依頼して、作業内容や費用を確認するとよいでしょう。
抜根を自分でやる方法
抜根を自分でおこなうときには、抜根に必要な道具なども自分で揃えなければいけません。抜根に必要な道具や終わったあとの処理方法、注意点についてみていきましょう。
抜根に必要な道具を揃えよう

まずは抜根するときに必要な道具をご紹介します。
・シャベル、スコップ
抜根する木の回りを掘るときに使用します。
・のこぎり
地中の根は長く伸びていることも多いです。長く伸びた根はのこぎりで切りながら作業をおこなうと抜根しやすくなります。
・軍手
滑り止めの付いた軍手であれば、作業がしやすくなるだけでなく、ケガ防止にもなります。
・除草剤
抜根が終わったあとに使用します。残った根が成長するのを防ぐためです。
抜根に必要な道具を揃えたとしても、やみくもに作業をしていては余計に時間や労力がかかってしまいます。ケガを防ぐためにも、抜根手順を確認しておきましょう。
抜根手順
抜根をするときは、幹の周辺から少し離れたところを内側に向かってスコップで掘っていきます。一カ所のみを掘るのではなく幹の回り全体を掘ることで抜根しやすくなります。
根が見えてきたらノコギリで根を切り取っていきます。まわりの根を切り落としたら、幹を押したり引いたりしながら揺らしましょう。木が揺れやすくなったら引っ張って幹を抜きとります。
抜根した庭木を別の場所に移植したいと考えているのであれば、根を傷つけないように抜根をする必要があります。無理に抜根をしてしまうと根が傷つき成長の妨げになるおそれがあるので、移植したいと考えている場合は業者に依頼したほうがよいでしょう。
抜根が終わったあとの処理や注意点
抜根が終わったあとは除草剤を撒きます。これは、根が残ってしまったとしても、枯らして成長しなくするためです。ただし、除草剤を撒くと周辺に生えているほかの植物も枯れてしまうことがあります。植物を育てているときには撒く範囲に注意しましょう。
抜根した木をそのままにしておくと、シロアリの住処になるおそれがあるため、処分しましょう。小さく切り分けることができれば、ごみとして出すことも可能です。地域によってゴミのルールが異なるので、地域の自治体に確認するとよいでしょう。
【要注意】竹の抜根は難易度高め

抜根する植物によっても難易度は変わってきます。サツキなどの背の低い植物は根の張りが浅い場合が多いため、比較的抜根がしやすい植物といえます。一方、難易度が高い植物として竹があげられます。
竹は地下茎を伸ばす植物です。竹の地下茎は他の植物よりも太く、広い範囲に伸ばします。場合によっては3メートルほどの深さまで伸ばすことがあるのです。
生命力も強いため、抜根したとしても根が残っているとそこからまた竹が伸びてくることがあります。そのため、竹を抜根するときには土を掘り起こし、根をすべて取り除かなければなりません。手作業ですべての根を取り除くことは大変なので、竹の抜根作業には重機を使用するのが一般的です。
抜根を自力でおこなうことは可能ですが、時間や労力がかかります。竹のように重機を必要とする場合もあるため、自力での作業に不安があるかたもいるのではないでしょうか。そんなときは業者に依頼するとよいでしょう。業者であれば重機を必要とするような抜根でも対応することが可能です。
弊社ではいつでもご相談いただけるよう、24時間お電話を受け付けております。お気軽にご相談ください。

自宅の木が大きくなりすぎると、手入れが大変ですよね。枯れてしまった場合、伐採したほうがよいのか悩まれている方もいるのではないでしょうか。
大きくなりすぎている木は庭の景観を損なうだけではなく、近隣の方にも迷惑をかけてしまうことがあります。伐採をしようとしても、作業の流れや方法などを知らずにおこなってしまうと、ケガや事故につながるおそれがあり、大変危険です。
そこで、この記事では伐採が必要な理由やプロがおこなう伐採の作業手順、木の処分までご紹介します。庭の景観を保つためにだけではなく、近隣の方とのトラブルを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
伐採作業は本当に必要?切る前の確認事項
伐採とは、木を切り倒すことです。木は場合によって、伐採する必要が出てきます。以下に伐採が必要な場合や、伐採をするときにおこなう準備についてみていきましょう。
こんなケースは伐採が必要

木を伐採する理由のひとつは、庭の景観をよくすることです。庭の木が大きすぎると日陰を作り、庭を暗い印象にしてしまいます。また、大きくなりすぎた木は庭の土の養分を奪います。そのため、ほかの植物に必要な養分まで奪われてしまうおそれがあるのです。
それだけではなく、木が大きくなりすぎて葉や枝が近隣の敷地に入ってしまうことがあります。柿などの実が生る木であれば、実が落ちて虫や小動物が寄ってくることもあります。近隣の方とのトラブルを防ぐためにも、大きくなりすぎる前に伐採したほうがよいでしょう。
伐採を決めたら:1.作業日の調整をする
自分で伐採をすることは可能ですが、一人で作業をおこなうことは危険です。そのため、家族や友人など、手伝ってくれる人を探し、その人たちと日程を調整して作業日を決めていきます。木は想像以上に重く、枝が落ちてきたり、木が倒れてくるときにケガをしたりするおそれがあるためです。
伐採を決めたら:2.道具を揃える
作業を始める前に、伐採をするときに必要なものを揃えておきましょう。必要なものは以下のとおりです。
防護服・防護メガネ
伐採をしていると、枝が落ちてきたり木くずが飛んできたりすることがあります。枝や木くずなどから身を守るため、防護服や防護メガネを着用するようにしましょう。
ノコギリ・チェーンソー
伐採作業にはノコギリやチェーンソーを使用します。ノコギリは比較的手軽に扱うことができますが、労力が必要です。
その分チェーンソーは簡単に木を切ることはできますが、キックバック現象を起こすことがあります。キックバック現象とは、作業をしている人に向かってチェーンソーが飛び上がる現象です。
ロープ・ゴミ袋
ロープは、木を倒すときの補助の役割として使用します。伐採した木を処分する際に使用するゴミ袋なども用意しておくとよいでしょう。
伐採を決めたら:3.伐採計画を立てる
伐採をする前に、木をどの方向へ倒すかを決めておくことが大切です。間違った方向へ倒れると周りにある家や植物が損傷することや、周りにいる人がケガすることがあるためです。
木の重心がどちらにかかっているかをみて、重心がかかっている方向へ倒すことが多いですが、必ずしもそれが正しいとはいえません。地面の傾きや木を倒せるスペースがあるかどうか、家や植物など周りにあるものが損傷しないかどうかなど、入念に計画を立てます。
伐採に機械を使うときは騒音が出るため、作業をおこなう前には近隣への挨拶もしておいたほうがよいでしょう。挨拶をせずに伐採作業を始めると、騒音が原因でご近所トラブルにつながるおそれがあるためです。
古来より日本では、木には家の守り神として精霊が宿るといわれていました。そのため、木を伐採するときには感謝と謝罪の意を込めて、お祓いをすることが多いようです。略式のお祓いであれば、四隅にお酒と塩をまき、手を合わせるようにしましょう。正式なお祓いをする場合は、神社へ依頼することも可能です。
自分でやるのはリスク大!
余分な枝が残っていると木の重心も定まらないため、伐採をするときには、余分な枝を切り落としてから幹を切っていきます。伐採を始めてからは手伝ってくれる人と連結をとり、声をかけながら作業をするようにしましょう。木は思っているよりも重いため、予期せず枝が落ちてきたり、木が倒れてきたりと、ケガをしてしまうおそれがあります。
難しい作業に手間取るだけでなく、このようなリスクを考えると、伐採作業は業者に任せたほうがよいでしょう。弊社にお電話いただければ、伐採に関するお悩みについて24時間365日ご相談をしていただくことが可能です。また、ご相談をお聞きしたうえで、ご要望に合った業者をご紹介させていただきます。
【プロがおこなう】伐採作業の手順
伐採作業を業者に依頼すると、どのような作業をしてくれるのか気になるという方も多いでしょう。以下に、業者がおこなう基本的な伐採作業の手順についてご紹介します。
【手順1】伐採計画を立てる
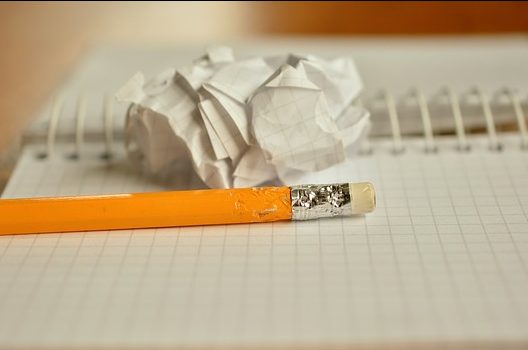
まずは、安全で確実に作業をおこなうために、木を倒す方向を決めます。木を倒す方向を決めるときは、木のサイズや重心、周囲にあるものなど、さまざまな要素から考慮されます。また、伐採の際に倒した木が人に当たらないように、見張り役をどこに配置するかなども、この段階で入念に決められることが多いです。
【手順2】倒す反対側の草や枝を除去する
木が倒れ始めると、作業者は反対側に避難します。そのため、倒す反対側にある庭の装飾品や石など、障害物となるようなものは取り除いておきます。避難する際、落ちている葉や枝を踏んで滑ったりつまづいたりすることもあるので、葉や枝なども取り除きます。
【手順3】不要な枝をなくす
安全に伐採作業をおこなうために、木の枝が多すぎたり、周りの木や建物にかかっている枝がある場合は、事前に不要な枝を切り落とします。そのままの状態で木を伐採すると、倒したときに周辺の木や建物、作業をしている人や手伝ってくれている人にぶつかるおそれがあるためです。
【手順4】受け口・追い口を作る
伐採をするときには、一か所のみの切り口で切り倒すのではなく、受け口と追い口を作って倒していきます。二か所の切り口を入れることにより、倒したい方向へ木を倒れやすくすることが可能です。
まず、倒す方向に受け口を作ります。受け口は30度~45度の∠のような形になるように、幹の3分の1くらいまで切り込みを入れます。その後、受け口の反対側に追い口を作ります。追い口は、受け口の3分の2くらいの高さのところから水平に切り込みを入れていきます。このとき、受け口まで届かないよう注意しましょう。
【手順5】木を倒す
受け口と追い口を作ったら、受け口のほうへ押せば木が倒れていきます。木が倒れてきたら反対側へ避難します。
業者はこのような手順で伐採作業をしています。このような手順を自分でおこなうことに少しでも不安がある場合は、業者に依頼するとよいでしょう。計画や準備、作業までをしっかりとおこなってくれるため、業者に依頼するメリットは大きいといえます。
弊社にご連絡いただければ、お住まいの地域に関わらず、伐採業者をご紹介することが可能です。伐採作業を検討されているという方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
伐採で出た木の処分は?
木を切り倒したら終わりではなく、伐採をした木は処分しなければなりません。ここからは、切り倒した木の処分方法についてご紹介します。
まずはしっかり乾燥させよう

木は湿ったまま長時間放置してしまうと、腐ることや、シロアリやカビが発生するおそれがあります。伐採した木はしっかりと乾燥させるようにしましょう。長期間保管するときは濡れない場所に保管するなどの必要があります。
細い木ならゴミとして出せる
細い木を30センチメートルほどの長さまで短くすることができれば、ゴミとして出すことができます。木は燃えるため可燃ごみとなりますが、自治体によって出し方などのルールが異なります。出す前にはお住いの自治体のホームページで確認したり、電話で問い合わせたりするなどしてルールを確認したうえで出すようにしましょう。
自分で加工する方法も
自分で加工することができれば、木材などとして販売することもできます。地域によっては木材を加工する道具を貸してくれる自治体もあります。もしお住いの自治体で道具を借りることが難しい場合は、ホームセンターなどから借りることも可能です。
大きな木は自力での処分が難しい......
細くて小さな木であれば、ご紹介した方法で木を処分することができます。しかし大きな木や太い木であれば、その分時間や労力がかかり、処分するのも大変です。
そのため、面倒だと感じる方は、伐採と合わせて業者に依頼することがおすすめです。業者によって作業内容や費用が異なるので、依頼する前に見積りをとり、作業内容や金額などを確認するとよいでしょう。
弊社であれば無料見積りだけではなく、現地調査もおこなっております。ご依頼される前に、抱かれている不安や疑問を解消していただけるよう、ご質問などにも誠意をもって対応いたします。お気軽にご相談ください。

伐採作業をしていると、“かかり木”が発生することがあります。かかり木は非常に危険な状態なので、正しい方法を知ってから対処しましょう。間違った方法で伐採をしてしまうと、ケガや事故を引き起こす原因になってしまいます。
このコラムでは、かかり木の正しい伐採方法をご紹介します。間違った伐採方法や注意点もお伝えしますので、一度最後まで読んでいただいてから作業にとりかかるようにしましょう。
▼かかり木の間違った伐採方法
かかり木は、いつどんなときに倒れてくるかわからないので非常に危険な状態です。まずは、やってはいけない間違った伐採方法をお伝えします。ケガや事故を防ぐためにも、必ず一度読んでおきましょう。
かかり木とは?

かかり木とは、チェーンソーなどを使って伐採したとき、思いどおりに傾かず周辺の木に寄りかかってしまった状態の木を指します。伐採するときは木を倒す方向を決めて切り込みを入れていきますが、切り込みの位置にズレがあると、かかり木を起こしてしまうことがあるのです。
危険!間違ったかかり木の伐採・処理方法
かかり木は、いつ倒れてきてもおかしくない状態です。突然倒れてきてしまうと、転倒やケガの危険性があり、木の下敷きになるなど命にかかわることもあるので、とにかく慎重におこなわなくてはなりません。大きな事故を招かないためにも、以下のようなことは絶対にやめましょう。
○枝切り
枝切りとは、倒れた木に寄りかかられている枝を切り倒すことです。枝切りをすると木がどの方向に倒れるかは予測がつかないので、非常に危険です。
○玉切り
玉切りとは、かかり木の元口(根元近く)を切ることです。自分がいる方向へと倒れてくる危険があります。また、元口を切らなくても、かかり木自体を伐採しようとすれば同様の事故が起こるおそれがあります。
○投げ倒し
投げ倒しとは、かかり木が起こったときに近くの木をあえて切り倒し、かかり木にぶつけて解消しようとすることです。これでは、かかり木が思わぬ方向に倒れたり、そもそもかかり木を解消できず隣の木もかかり木になってしまったりするおそれがあります。
○木を倒したい方向へ動かす
作業する人がかかり木を肩で支えて向きを変えるなど、直接的に力を加えることもやめましょう。木の重さに耐えきれず、木の下敷きになってしまうおそれがあります。
このように、「どうにかしよう」と無理に力を加えてもかかり木は解決できません。そればかりか、さらなるケガや事故を招くおそれもあります。もちろん、かかり木の放置も絶対にやめましょう。かかり木がおこったら、正しい手順で慎重に処理することが大切です。
▼かかり木を安全に解消する方法
続いては、安全にかかり木を解消する正しい伐採方法をご紹介します。1章の“間違った伐採方法”を知ってもらったうえでここを読めば、なお安心です。ぜひ、かかり木伐採マニュアルとしてご活用ください。
かかり木の処理に必要なもの

作業に入る前に、まずはかかり木の伐採に必要なものを準備しましょう。
○肌を保護できる服(作業着など)
肌が露出していると、木でケガをしたり転倒したりするおそれがあります。また、虫刺されや雑草による肌荒れを起こすこともあるので、できるだけ肌を露出しない服を準備しましょう。
○ロープ(またはベルト)
幹にロープやベルトを巻きつけて、木を確実に地面に倒すために使用します。
○フェリングカバー(または木廻しフック)
安全に木を倒すために、かかり木の切り口にひっかけて使用します。なかには、フックとロープが一緒になったような便利な道具もあります。
○ガイドブロック
ロープがしっかりと確実に引っかかるように設置するブロックです。滑車がついているので、安全に作業ができるようになっています。
かかり木処理前の安全確認
必要なものを準備できたら、かかり木を安全に処理できるよう周辺の安全確認をおこないましょう。
- 作業場所周辺に障害物がないか
- 作業場所周辺は十分な広さがあるか
安全確認をおこなっていないと、かかり木以外に別のトラブルを引き起こしてしまうおそれがあります。木を十分に倒せる広さがあるか、人や建物など障害物がないかどうか丁寧に確認しておきましょう。安全のため、万が一倒れてしまった場合の退避場所を事前に決めておくことも大切です。
かかり木を安全に処理する方法
安全確認までしっかりおこなったら、手順どおりにかかり木を処理していきます。かかり木の幹の太さ(目安:胸の高さの直径)によって少し手順が異なるため、サイズを把握してから作業に入りましょう。
【1】約20センチメートル未満
幹の太さが約20センチメートル未満と比較的小さな木の場合は、ロープをかかり木にかけて倒したい方向に回転させながら倒します。このとき、できるだけ広く安全な方向に倒すようにしましょう。
【2】約20センチメートル以上
比較的太いかかり木を処理するには、技術と力が必要です。ガイドブロックを設置し、ロープが確実に安全に使用できるようにします。周辺を再度確認しロープを数回かかり木に巻きつけたら、回転させながらかかり木を倒しましょう。
このように、かかり木を安全に処理するには知識と技術が必要です。自信がない方や不安な方は伐採のプロに依頼することをおすすめします。プロなら、かかり木を適切に処理する知識と技術があります。必要な道具もそろっているので、事前の準備に手間や時間をかけずにすぐに作業に取りかかることができるので安心です。
▼伐採の基本をおさらいしよう!
ここまでは、かかり木を安全に処理する方法を詳しくお伝えしましたが、しっかりと理解できましたか?安全に適切にかかり木を処理することは大切ですが、それよりも“かかり木を起こさないこと”が最も重要です。ここでは、かかり木を起こさない予防も兼ねて、おさらいとして伐採の基本をお伝えします。基本をしっかりマスターしておきましょう。
自分で伐採できるかの判断

まずは、“自分で伐採できるかどうか”を判断することからです。自分で安全に伐採できるかどうかは以下を目安にしてください。
- 高さ:約3メートル未満
- 太さ:約20センチメートル未満
これ以上の大きさは、万が一思わぬ方向へ木が倒れてきたときに支えられません。自分で安全に伐採できるかどうかをきちんと判断してから作業しましょう。
自分で安全に倒せるかどうかを判断できたら、“木を倒す方向”を決定します。木を倒す方向は、第2章の“かかり木処理前の安全確認”と同様です。周辺の障害物の有無や十分な広さを確保できているかをしっかりと確認しておくことが、確実な伐採のポイントとなります。
伐採に必要な道具
続いて、伐採に必要な道具と伐採の手順をお伝えします。
○伐採に必要な道具とその役割
- チェーンソーやノコギリ:木を切る
- ロープ:木を安全な方向に倒す
- シャベル:木の根っこを掘り出す
- ゴム袋:伐採時に発生する枝葉などを処分する
どれも、ホームセンターや通販で購入可能です。それぞれ大きさや性能の違いにより値段も異なります。サイズや使い勝手に不安があるなら、お店の方に相談しながら決めましょう。
基本的な伐採手順
続いて、基本の伐採手順をご紹介します。安全に作業を終えるためにも、常に周囲の安全に気をつけて、慎重におこないましょう。
- 倒す方向にロープをかけておく
- 倒す方向に“受け口”を入れる
- 受け口の反対側に“追い口”を入れる
- 追い口側から力を加えてゆっくりと倒す
- 残った根を掘り出す
受け口は、幹の直径の約4分の1を目安に切り込みを入れます。木が確実に倒れるように、切り込みの角度は30度~45度くらいが適切です。
追い口は、角度をつけずに受け口に向かって真っすぐ切り込みを入れていきます。このとき、受け口の約3分の2の高さに追い口を入れますが、受け口まで到達しないよう注意しましょう。木を伐採できたら、残った根もきれいに掘り出します。
あと片付け・処分方法
最後に、伐採した木はきちんと処分しましょう。根や枝葉は、基本的に“可燃ごみ”として処分可能です。ゴミ袋にまとめて、各自治体の処分方法に従って処分してください。できるかぎり小さくまとめられるよう、枝や根は細かく切り、葉はしっかり乾燥させて軽くつぶしておくとよいでしょう。
▼伐採をプロに依頼したら時間・費用はどれくらい?
伐採は、事前の準備や安全の確保、あと片付けなど作業前から作業後まで、多くの手順があり素人がおこなうのは大変です。転倒やケガ、場合によっては大きな事故につながるおそれもあるので、できるだけ伐採のプロにまかせることをおすすめします。ここでは、伐採をプロに依頼する場合にかかる費用や作業時間について詳しくお伝えします。
伐採にかかる費用

プロに伐採を依頼する場合、伐採したい木の大きさによって費用に差が出てきます。費用相場は以下のとおりです。
- 高さ3メートル未満:約3,000~5,000円
- 高さ5メートル未満:約15,000円~20,000円
- 高さ5メートル以上:約20,000円~
これらはあくまで相場ですので、幹の直径が太かったり特殊な道具や重機が必要だったりするなど、難易度の高い伐採となる場合には費用が高くなります。
また、なかには“1本あたり”ではなく“職人の時給や日給”によって料金を設定している業者もあります。どのように料金を設定しているかを知るためにも、正式な依頼前に見積りをとっておくことが大切です。
さらに、業者によっては、ゴミ処理や木の回収、抜根作業などについては別途費用がかかることもあります。見積りをとったとき、どこまでの費用が含まれているのかをしっかりと確認するようにしましょう。
伐採にかかる時間
伐採にかかる時間も、作業場所や作業人数、伐採する木の種類などによって違います。たとえば、作業場所が狭く、重機や道具を運び入れることができない場合は、その分難易度も上がり時間がかかってしまうのです。
もし、依頼した業者が“職人の時給や日給”で料金を設定していた場合、時間がかかるほど費用も高くなります。また、伐採作業は屋外ですから、できるかぎり短時間で終える方が天候の変化などを気にすることもなく安心です。この点も踏まえて、事前に所要時間の目安も確認しておきましょう。
伐採作業には危険がいっぱい…プロへの依頼がおすすめ
プロに伐採を依頼すると、費用はかかりますが確実で安心な伐採が可能です。知識や技術もあるので、素人がやるよりも確実に短時間で作業を終えることができるでしょう。
費用の心配がある方は、無料の調査や見積りを活用するのがおすすめです。不安点や疑問点を相談し、実際にかかる費用の詳細を聞いておくと安心できます。予算があるならば、その場で伝えておきましょう。
弊社では、無料で調査・見積りをおこなっておりますので、初期費用の心配はご無用です。お見積書は、丁寧かつわかりやすく作成することを心がけておりますので、どなたさまも安心してご相談ください。危険な伐採作業を安全におこなうためにも、ぜひ弊社にお任せください。
▼まとめ
かかり木の伐採は、知識や技術が必要とされる作業です。いつ倒木するかわからない危険な状態ですので、正しいかかり木の処理方法を学び、手順どおりにおこないましょう。「自分で処理できそうにない……」と思ったら、早急に伐採のプロに依頼してください。
また、かかり木の処理も大切ですが、まずはかかり木をおこさない“予防”が最も大切です。かかり木の処理に限らず伐採に自信がない方は、プロに相談・依頼し安全に作業してもらうことをおすすめします。

生命力の強い桐の木は、伐採した後にも思わぬところから枝が出てくることがあります。伐採をするときは、あらかじめ枯らしてからおこなうなどの工夫をするとやりやすいです。今回は、桐の木の正しい伐採方法を確認していきましょう。
除草剤を使って切を枯らす方法を中心に、伐採が円滑に進められる方法をいくつか紹介していきます。桐の木の処分を検討している方はぜひ参考にしてみてください
桐の木は枯らしてから伐採がおすすめです
桐を切るときには、除草剤を使って「枯らす」というひと手間を加えてください。そのまま切るよりも、枯らしてからのほうがよいのには理由があります。その理由と、枯らすのに最も効果的な除草剤の使用方法をここで紹介します。
桐は切っても切ってもキリがない!?

はたとえ伐採して切り株にしても、すぐに芽が生えてきてしまうことがある、生命力の強い木です。切っても切ってもキリがないというのは、それが理由です。長年放置すれば、再び桐の木は大きくなってしまうでしょう。そのようなことを防ぐためには、根を撤去する「抜根」をおこなうことをオススメします。
桐は枯らしてから伐採がおすすめな理由
桐が健康な状態で伐採をおこなうと、伐採後に残る切り株から、さまざまな悪影響が出ます。例えば木を好んで食べるシロアリが棲みついたり、快適な場所を探している蜂が巣を作ったりするのです。健康な桐の切り株を放置してしまえば、シロアリや蜂の被害に遭うかもしれません。
桐を枯らすことで、こうした虫が棲みつくことを防ぐことができるといわれています。そのため、事前に桐は枯らしておくとよいでしょう。
一般的なのは除草剤を使った枯らし方
除草剤なら枯らせることができます。一般的に除草剤を使った枯らし方がとられる場合が多いので、方法を知っておきましょう。用意するものは、穴を空けるための電動ドリルと、「グリホサート」という成分が入った除草剤、そしてスポイトです。

まず、幹に除草剤注入用の穴を開けます。穴はドリルを使って、根元付近の幹にから根っこに向かうように斜め下向きに開けましょう。穴は深さ10センチまでのものを、7センチから8センチ間隔で10か所ほど開けます。
それぞれの穴に除草剤の原液を1ミリリットルずつ入れます。除草剤を入れるときは、スポイトがあったほうが作業しやすいでしょう。
注意点としては、グリホサート系は非選択型という、どんな植物にでも効くタイプの除草剤だということがあります。農地などの近くでおこなおうとすると、作物の生育も阻害してしまうこともあります。近くの植物を枯らしたくない場合は、除草剤は使わず、後で紹介する皮を剥ぐ方法を試してみてください。
生命力が強い桐、抜根するのも大変!
再び桐の木が成長することを防ぐには、切り株ごと撤去する必要があります。切り株を取り除くためには、根ごと引き抜かなければなりません。そのため太い木の根を抜くときには、ショベルカーを使用することもあるのです。桐を伐採する作業は、意外と大変だということがおわかりいただけたのではないでしょうか。
桐の木を伐採する作業は、業者に依頼することをおすすめします。弊社は伐採ができる業者の紹介をおこなっております。弊社紹介の加盟店をご利用していただくと、簡単に見積りを取ることができますので、まずはフリーダイヤルの電話相談窓口からお問い合わせください。
除草剤を使いたくない場合の木の枯らし方
除草剤を使うと、周りの土壌に影響が出ることがあるので、できれば使いたくないという方もいらっしゃることでしょう。除草剤を使わずに木を枯らす方法もあるので、ここで紹介していきます。
表皮を剥ぐ方法
木の構造上、栄養を運ぶ管は木の皮の部分に集中しているので、これを剥がして栄養がいきわたらないようにします。ナイフやノコギリを使って、幅が20センチから30センチほどの帯状の皮が取れるように剥がしてください。こうすることで、しだいに木は栄養を失って、枯れていきます。
木の水分が増える4月から8月にやると、皮が剥がしやすいのでよいでしょう。この処理をして半年から1年ほどで木の全体が枯れます。少し時間のかかる作業になりますが、林業などでも使われる方法です。
ロープを巻く方法
木にロープやポリエチレンのヒモなどを巻き付けておくことで枯れさせる方法です。巻き付けたままで放置しておくと、木が成長して紐が食い込んでいき、養分が送られなくなって枯れます。この方法は木が成長して太くなることで枯らすので、数年単位の時間がかかります。
計画的に木や林を育てる林業であれば有効なやり方です。一方、庭木などを切るには時間がかかりすぎるため、あまり向かないでしょう。
木を枯らす場合の注意点
除草剤を使わない方法では、必ず枯らすことができるという保証はありません。皮をはぐ方法も、ロープを巻く方法も、枯れずに生き延びてしまったり、桐の性質上、土のほかの場所から幹が生えてくることもあります。
また、木は乾き、枯れた状態に近づくと、倒れやすくなります。幹が乾燥してしなやかさがなくなり、もろくなるからです。枯らすときは、木が思わぬときに倒れてしまうことに十分注意をしてください。
桐を枯らして処分する方法のデメリット
桐を枯らしてから処分する方法には、デメリットもあります。それは、桐が枯れたかどうかを見分けるのが難しいということです。また、枯れるのにも時間がかかります。
すぐにでも伐採してしまいたいというときは、業者に依頼すると対応してもらえるでしょう。業者に伐採と抜根を任してしまえば、作業の負担を軽減するために枯らす必要もありません。
必要な作業ができる業者を探すときは、弊社の紹介サービスを使うと便利です。弊社の加盟店であれば、現地調査から見積りまでを無料ですることができます。見積りに満足できなければキャンセルもできますのでまずはお電話からご相談ください。
桐の木を自力で伐採する方法
自分で切るときには、その木が自力で木を切るときは、伐採できるサイズかどうかを見極めることが大切になってきます。ここでは伐採できる木の見分けかたと、伐採の方法を解説していきます。木が倒れる方向をコントロールするための独特な切り方があるので、これを読んで知識を持ったうえで作業をしましょう。
自力で伐採できる基準
伐採をする前には、その木が自力で伐採できるサイズのものかどうかを判断しましょう。伐採は木を切り倒すときなどに危険が生じるので、この見極めが重要になります。自力伐採ができる基準としては、以下を参考にしてください。
木の高さ:3メートルまで
幹の直径:20センチまで
高い木は倒れるときの衝撃が大きくなり、枝の処理も難しいですし、あまりにも太い場合はノコギリが通らないことがあります。これ以上の大きさの木は、自力では伐採しようとせず、業者に頼むのが無難です。
作業に必要な準備

まずは切る木を決め、道具を準備しましょう。道具は、ここに紹介するものを準備してください。また、服装は作業着がおすすめです。
■ノコギリ
伐採用のノコギリというものがありますので、それを用意します。大きなものから小さなものまであるので、木に合ったサイズを選びましょう。刃が電動で動くノコギリもあるので、何本も切るような場合はこれを使うとよいです。
■ロープ
ロープは木を結んで引っ張っておくことで、倒れる方向を調整するのに役立ちます。必須ではありませんが、用意しておくとより安全に作業ができます。
■スコップ
木を切り倒した後に残った切り株を掘り起こすために用意してください。切り株を残すのであればこれは必要ありません。
■ゴーグル・マスク・軍手
を守るためのアイテムです。ノコギリを触ったり、木のささくれが刺さったりするとケガの危険があるので、木を切るときにはこれらを着用しましょう。
■帽子またはヘルメット
頭上から枝が降ってくることも見越して、ヘルメットなども用意しましょう。低い木であれば帽子やタオルでもよいですが、頭を守ることは常に忘れないようにしてください。
伐採の手順
伐採の手順としては、まず木を倒す方向を決めます。その後実際に切りはじめ、倒れたら根を掘り起こして除去します。順番に説明していきましょう。
■倒す方向を決める
木を倒す作業は、計画的におこなわないと思わぬ方向へ倒れてしまいます。まずは、木が倒れるのに十分なスペースがある方向を見つけましょう。方向を決めたら、ロープの片方の端を、桐の幹の立って届く範囲でできるだけ高い場所に縛ります。
もう片方のロープの端は、倒す方向にある木などに、ロープがつっぱるようにしてくくり付けましょう。こうすることで、木が倒れるときにロープが幹を引っ張るので、思った方向に倒せる確率が高まります。
■木を切る
切るときは、幹にふたつの切れ込みを入れましょう。まずは幹の倒す方向側に、横から見て30度から45度くらいになるように切れ込みを入れます。切れ込みは幹の3分の2くらいまの深さで入れて、片方の線を斜めに、もう片方を地面と水平に入れてください。
それができたら、反対側から、今度は水平に切っていきます。位置は、地面と水平なほうの切れ込みの線よりも上で切りすすめます。一直線状に切ってください。
直線状の切れ込みをある程度まで切りすすめていくと、倒したい方向に木が倒れ始めます。倒れ始めたらその場をいったん離れて様子を見ましょう。木が倒れ終わったら次の工程に入ります。

■根を掘り起こして撤去する
根を掘り起こします。枯らしてから切らない場合などは、根をしっかりと取り除かないと、また生えてきてしまうので、この作業をしましょう。根はスコップで掘り起こしていきます。
木の根元の土を掘り起こし、切り株を引き抜きます。抜けないほど深く根が伸びているときは、ノコギリを使って切るか、除草剤で枯らすとよいでしょう。枯らしかたは、「除草剤を使った枯らし方」で説明しているやり方で大丈夫です。
伐採した木の処分方法を確かめておこう
伐採した木の処分方法は、木の大きさによって変わります。自治体がおこなっているごみ回収で回収してくれる場合もありますが、大きすぎるゴミだと回収されない場合もあるので注意してください。
自治体が回収してくれないときは、業者に依頼して処分してもらうことになるでしょう。また桐は販売できる場合があるなど、いろいろな処分の方法が考えられます。事前に調べて、処分方法も決めてから伐採してください。
難しい場合はムリせず依頼!業者の費用はいくら?
木の伐採は難しい作業です。作業自体が危険を伴いますし、道具をそろえる必要もあります。また大きな木の場合は、自力での伐採ができないこともあります。
伐採を業者に頼むときに気になるのが費用でしょう。木の伐採は高さによって値段が定められていることがほとんどです。成熟した桐の木は、樹高が10メートルから15メートルとなります。これはほとんどの業者で価格を提示しておらず、別途見積りが必要な高さです。
ちなみに、7メートルほどの木を伐採するには、およそ30,000円の費用がかかるので、30,000円以上の費用がかかるものと考えてください。正確な費用は、業者から実際に見積りを取って確認しましょう。
弊社の加盟店なら、現地調査と見積りは無料です。無料相談窓口にお問い合わせいただくことで、お客様に最適な加盟業者を派遣することができます。伐採に関して、少しでも困ったことがございましたら、まずは弊社にご相談ください。

木を伐採するときに、活躍するのがチェーンソーです。チェーンソーを使って自力で伐採をおこなおうと考える方も多いと思います。
しかしチェーンソーを使って伐採するときは注意が必要です。チェーンソーの扱いを間違えると、大けがを負ってしまうおそれがあるのです。
そこでこちらのコラムでは、チェーンソーを扱う危険性や正しい使用方法をご紹介していきます。安全に伐採をするためにも、チェーンソーの伐採に関する知識をたくわえておきましょう。
▼チェーンソーでの伐採は素人でもできる?
素人でも伐採をすることは可能です。ただし、注意をしておこなわなければなりません。もし扱い方を間違えてしまうと、大惨事を引き起こすおそれもあるのです。
チェーンソーを扱う危険性

チェーンソーは、電気やガソリンを利用して刃を動かす道具です。人力でなくエネルギーを使って刃を動かすため、非常に大きなパワーを出すことができます。そのため、人力では難しいような木の伐採もおこなえることが魅力です。
しかし、チェーンソーの取り扱い方を間違えてしまえば、自分自身を傷つけてしまうおそれがあります。うっかり落としてしまえば、木を伐採するほどの威力が、身体に向かう危険もあるのです。
またしっかりと持って作業をしていたとしても、道具の構造上、刃が自分に向いてしまうときもあります。それがキックバックです。このキックバックについては、後ほど詳しく説明をおこないます。
チェーンソーによる事故は少なくありません。扱い方に不安のある方は、無理して自分で作業をするよりも、業者へ依頼をしたほうがよいでしょう。
プロに伐採を依頼したときの費用の相場
業者へ依頼をすることで、安全に伐採の作業をおこなうことができます。また、労力や時間を費やす必要もなくなるため、非常に便利です。しかし業者へ依頼をするとなると、費用が気になる方も多いでしょう。
プロに伐採を依頼したときの相場は、おおよそ5,000~30,000円だといわれています。伐採の費用は、木の高さによって大きく変わってきます。そのため、樹高が3メートル程度の木であれば10,000円以内に収まることも多いですが、10メートルを超えるような大木であれば、30,000円を超えてしまうこともあるようです。
また抜根や木の回収、作業の手間によっても変わってきます。詳しく知りたい方は、無料で見積りを取ってみると、費用の見当をつけることができるでしょう。
弊社では、無料で見積りを承っております。見積りを取るお時間がない方は、ぜひご利用してみてはいかがでしょうか。
▼チェーンソーで伐採するときに準備するもの
安全に伐採ができるという方は、自力でおこなうのもひとつの手です。しかし、危険性がある分、事前準備はしっかりとおこなわなければなりません。自力で伐採をおこなう方は、以下を参考に、伐採に備えて服装や持ち物の準備をしていきましょう。
チェーンソーを扱うときの服装

服装は、防護服と防護メガネが必須だといえます。チェーンソーで伐採の作業をするときは、木のクズが飛んできてしまうことがあります。また、チェーンソーの刃が身体に触れてしまうこともあるかもしれません。丈夫な防護服を着ていることで、身体を守ることができます。
ほかには、耳栓も用意しておくべきでしょう。伐採の作業は物理的な危険性だけでなく、音による被害を受けることがあります。間近でチェーンソーの騒音を聞き続けると、聴覚障害を患ってしまうおそれもあるのです。より安全に作業をおこなうためには準備しておいたほうがよいでしょう。
また高所で作業をする方は、ヘルメットがあると安全です。高所で作業をする場合は、落下してしまう危険性も考えられます。万が一に備えて、ヘルメットも装着しておくと安心です。
伐採は非常にケガをしやすい作業です。トラブルを起こさないことが大切ですが、万が一のことを考えて、準備をおこなうようにしましょう。
チェーンソーの特徴と選び方
伐採に欠かせないのが、チェーンソーです。チェーンソーはチェーンの形をしている刃で、固い物を切ることができる便利な機械です。しかしチェーンソーといっても、利用する人がより使いやすいように、さまざまな商品があります。
いざチェーンソーを購入しようと考えても、「どのようなものを選べばよいのかわからない」と感じる方も少なくないでしょう。そのようなときは、「自分に合った大きさか」「使用環境にふさわしい動力源か」という点を意識して、選ぶとよいです。それぞれのポイントについて説明をします。
■大きさ
まずチェーンソーには、さまざまな大きさの商品があります。サイズが大きいとパワーも大きくなる傾向があります。そのため、大きな木を伐採したいときには非常に便利です。ただし、小柄な女性や、お年を召した方には、あまりおすすめできません。
チェーンソーのサイズが大きいと、それを支えるだけの力も必要になります。無理して大きいサイズのチェーンソーを使おうとすると、落としたり、バランスを崩したりする危険性もあるでしょう。そのため、自分で支えることができるパワーのチェーンソーを選ぶようにしてください。
■動力源
チェーンソーの動力源は、大きく分けて2種類あります。1つ目が、電気を動力に駆動するものです。電気を動力とするチェーンソーは、充電タイプのものと、コードタイプの商品があります。
コード式のチェーンソーは、コンセントが身近にある環境であれば、使用することができます。コードをコンセントに挿入した状態でチェーンソーを使用するため、充電切れになることなく、使い続けることができます。「家の庭にある木を伐採したい」という方にはおすすめです。
コンセントがない環境であれば、充電タイプのチェーンソーがおすすめです。ただし充電タイプのチェーンソーは、充電が途中で切れてしまえば、作業を続行することができません。そのため、事前にしっかりと充電をしておくことが大切です。
また2つ目の動力源として、燃料があげられます。作業の前に燃料を補充しておくことで、電気がなくても使用することができます。燃料を準備しておけばいくらでも作業をすることができるので、電気がとおっていないような環境で伐採をおこなう方には、非常におすすめです。
チェーンソー以外に準備するものはある?
実は伐採では、チェーンソー以外にも必要なものがあります。たとえば木を倒すときに使用する、ロープ・滑車・くさび・ウィンチなどです。チェーンソーのみで伐採をしようと思うと、予期せぬ方向に木が倒れてしまうおそれがあるので、大変危険です。狙った方向に倒すためにも、これらの道具が必要になります。
また、手ノコギリがあると便利です。狙った方向に倒すには、正確に切れ目を入れることが大切です。しかしチェーンソーはパワーがある分勢いも強いため、細やかな調整が難しいのです。手ノコギリであれば調整もきくため、ひとつは用意しておくと、便利でしょう。
ほかにも、高い木を伐採するときは、まず枝を切ってから木を倒します。枝を切る際には、ハシゴが必要になるのです。
▼チェーンソーを使った伐採方法の流れ
必要な持ち物が準備できたら、次はいよいよ作業に取り掛かりましょう。作業では、まずチェーンソーの点検をおこなって安全を確認したのちに、伐採をはじめていきます。流れに合わせて、それぞれの作業を説明していきます。
チェーンソーを使う前の点検方法

チェーンソーの点検は、「部品が壊れていないか」「正しく作動するか」「チェーンソーを使うことができる環境か」という点を意識して、おこなっていきましょう。
チェーンソーはレバーやブレーキ、チェーンなどの部品が使われています。これらの部品が破損をしていないか、確認してください。部品が破損していないようであれば、実際にチェーンソーを駆動させて、動作確認をおこなっていきます。
その際に正しく作動をしないようであれば、伐採作業でトラブルを起こすおそれがあります。伐採に移る前に、詳しい点検をしましょう。
また、チェーンソーの種類によっては、ガソリンを使うものもあります。そのようなチェーンソーを使うときは、火気に注意をしてください。
これらの点検をおこなわないと、伐採の作業に危険が生じることがあります。安全に作業をおこなうためにも、確実に点検をおこないましょう。
1.木を切る方向を決める
伐採の作業は、木を切る方向を決めることから始まります。切って倒す方向には、物を置かないようにしましょう。もし物がある状態で作業をおこなってしまうと、木が引っかかって、完全に倒すことができません。木が引っかかった状態を解消するには労力を要しますので、周辺の物は取り除いておくことが大切です。
また、逃げ道の確保をしておくことも大切です。伐採の手順がうまくいかなければ、自分のいる方向に木が倒れてきてしまうことも考えられます。その際に逃げ道が必要になるため、確保しておきましょう。
2.「追い口」と「受け口」を作り木を倒す
倒す方向を決めたら、次は「追い口」と「受け口」を作ります。追い口とは、木を倒す方向とは逆の方向に入れる切れ込みです。また受け口とは、木を倒す方向側へ入れる切れ込みのことです。
これらの切れ込みを入れることで木がバランスを崩し、倒れるようになります。そのため、木を狙った方向に倒すためには、この切れ込みが非常に大切なのです。
作業は、受け口を作ったあとに、追い口を作るという流れですすめます。受け口は、まず、地面と平行に切れ目を入れていきます。次に、三角形になるような形に、斜めへ切れ込みを入れましょう。イメージとしては、口を開けているさまを横から見たような形になります。
受け口を作ったら、木を倒す方向にめがけて、追い口を作りましょう。追い口は、地面と水平に切れ込みを入れてください。これらの切れ込みを入れたら、次はロープや滑車、クサビなどを使って木を倒していきましょう。
かかり木になってしまったらどうすれば良い?
伐採途中に、倒したい木が途中で別の物に引っかかってしまい、倒れなくなってしまうことがあります。これを「かかり木」と呼びます。かかり木になってしまった場合は、木回しやけん引具などの道具を使って、木をずらしていきましょう。ずらす道具は、木のサイズに合ったものを使うとよいです。詳しい対処法に関しては、「」をご覧ください。
かかり木はそのまま放置してしまうと、非常に危険です。放置していると、予期せぬときに木が落下してしまうことがあります。木の落下位置に人がいれば、大惨事になってしまうのです。
しかしかかり木の対処も簡単ではなく、危険が伴います。対処に不安のある方は、すぐに業者へ依頼をしましょう。弊社は24時間電話受付をおこなっているため、迅速にお近くの業者をご紹介することができます。もしかかり木で悩まれていたら、ぜひお問い合わせください。
▼チェーンソーのキックバックに注意しよう!
チェーンソーは木を伐採できるというメリットがありますが、非常に危険な道具でもあります。チェーンソーを利用したトラブルでも、特に「キックバック」には注意が必要です。
キックバックとは

キックバックとは、自分に向かってチェーンソーが跳ね返ってしまう現象のことです。この現象は、自身に刃を向けるつもりがなくても、道具の構造上起こりうるものです。
そのためキックバックが起こる仕組みや防ぎ方を心得ていなければ、大惨事を引き起こしてしまうおそれがあります。
キックバックが起きてしまう原因
キックバックがとくに起こりやすいのは、チェーンソーの特定の位置に物が当たったときです。その特定の位置とは、チェーンソーの丸みを帯びた先端の、上半分です。この部分はキックバックゾーンと呼ばれており、このゾーンに固い物があたると、高い確率でキックバックを起こしてしまいます。
また、切れないものに当たってしまったり、刃が木に挟まれたときにもキックバックは起きてしまいます。ちょっとしたことでキックバックを起こしてしまうため、チェーンソーを使うときは、油断をしないようにしましょう。
キックバックを防ぐためにできること
キックバックを防ぐためには、「キックバックゾーンに固い物を触れさせない」「チェーンソーが挟まらないように努める」ことが大切です。また、以下のようなポイントも意識するとよいでしょう。
■正しい使い方を心掛ける
チェーンソーを使うときは、説明書に書いてあることを守り、正しい使い方をするようにしましょう。たとえば、「持ち手部分は正しい位置で握る」「しっかりとチェーンソーを握る」「立ち位置には気をつける」「まっすぐ切る」などです。
初歩的なことですが、これを意識しなければ、作業ミスが出てしまう場合があります。作業ミスがキックバックにつながることもあるので、正しい使い方をするようにしましょう。
■難易度の高い木の伐採は控える
なかには、大きかったり切り途中だったりする木を、伐採しようと考える人もいると思います。しかしこういった木は、素人が作業をするには難易度が高いでしょう。
難易度が高い木は、無理して作業をおこなったり、上手に作業が遂行できなかったりすることが多いです。同時に失敗する危険性もあがって、ケガをするリスクも高まるでしょう。無理して作業を続けてしまえば、キックバックを招くこともあるのです。そのようなときは、無理せずに業者へ依頼をしたほうが、安全であるためおすすめです。
チェーンソーの使用時に危険を感じたら……
いざチェーンソーを使用して伐採をしているときでも、「少し難しいな……」「ちょっと無理をしなければならないな」と感じるときがあるかもしれません。
そのようなときは、すみやかに作業を中断しましょう。無理して伐採を続けてしまえば、チェーンソーをうまく取り扱うことができずに、事故を招いてしまうおそれがあります。
安全を考慮すると、業者へ依頼をすることをおすすめします。業者であれば危険を冒すこともなく、楽に伐採をすることが可能です。
業者選びでお悩みの方は、ぜひ弊社へお問い合わせください。弊社では365日電話相談を受け付けています。無料で相見積りも承っているので、楽に業者へ依頼をすることができます。

大きくなりすぎた庭木にどうしていいか分からないという方も多いでしょう。庭木の成長は早く、いつの間にか大きくなっているという場合もあるのです。また、メンテナンスをしていたつもりでも、間違えた剪定方法は庭木を大きく成長させるおそれもあります。
本記事では、剪定すべきか伐採するべきかの判断基準、庭木を小さくする剪定方法、コンパクトに維持する方法を解説していきます。
さらに、メンテナンスを楽にする方法も紹介していきます。庭木が大きくなると手に負えなくなり、トラブルが起きやすくなりますので、早めに正しい剪定をしておくことが重要です。庭木の今後に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
大きくなりすぎた庭木は2択!剪定または伐採
大きくなりすぎた庭木は、剪定するか、伐採するかの2択となります。剪定とは、庭木の形を整えたり枝木を切る手入れのことです。この剪定をおこなう場合は、庭木に改善の余地があり、小さくできる可能性がある場合になります。
いきなり伐採という答えを出す前に、庭木を残し剪定することで問題解決につながる場合もあるということは知っておいたほうがよいでしょう。
また、伐採しなくてはいけないケースとして、庭木がすでにトラブルを抱えてしまっている場合は、早めに問題解決に臨んだほうがよさそうです。庭木の放置はとてもリスクが高く自分の敷地だけでなく、周囲の家へも影響を出しかねないためです。
大きな庭木を放置するリスク

大きな庭木はそのままにしておくとシロアリのエサとなってしまうかもしれません。庭木は屋外にありますので、雨に濡れる機会も多く、湿気も余分に保っているおそれがあります。
そのため、そのまま放置しておくと腐食してしまっている場合もあり、シロアリのエサとなりかねないのです。シロアリに食い荒らされた木の内部はもろく、倒木の危険性もでてくるでしょう。庭木のサイズによっては、自分の敷地内だけでなく、周囲への倒木の被害も考える必要があるかもしれません。
また、エサを食い尽くしてしまったシロアリは屋内へと移動してくるおそれもあるので注意が必要です。シロアリは乾燥を嫌い地中内へと移動し、そこから屋内へ侵入してくる場合があるためです。
これは、周囲に家がある場合は同様の被害も考えられます。被害を拡大させないためにも、大きな庭木を放置することはあまりおすすめできません。
大きくなると手に負えなくなるのはこんな種類の木
庭木には種類があり、低木、中木、高木の3種類にわかれています。そのなかでも、シンボルツリーとして使われることが多いのが高木となっています。高木のなかでも手に負えなくなるおそれが高い庭木を紹介していきます。
〇アカマツ
お庭でのシンボルツリーとしてよく使われているのがアカマツになります。日本で多くみられる松の種類に該当し、風情のある外観から人気のある庭木のひとつとなっているようです。幹や樹皮が茶色だけでなく、赤っぽい色を含んでいることも特徴的です。
アカマツの成長するスピードは早く、自分での剪定はなかなかむずかしいため、剪定を依頼するなどして維持費がかかってしまうでしょう。そのため、維持をすることがむずかしくなり、放置してしまう場合があるのです。
〇イチョウ
庭木のなかでもとくに早い成長スピードをもっています。一般的には、銀杏がなる木としてよく知られていることが多いのではないでしょうか。また、イチョウ自体も大きくなりやすく、枝を切ろうにも背が高くなり剪定がむずかしくなっていきます。
そのため、イチョウの木をコンパクトに維持するには、目的の高さにイチョウが育った段階で幹のてっぺん部分を切り落とす必要があります。幹のてっぺん部分を樹芯とよび、これを切り落とすことで、イチョウの木は縦に伸びる成長を止めるのです。
もしも、樹芯を切り落とさず放置していた場合、大きくなった庭木を自分で小さくしていくのはむずかしいものとなってしまいます。
〇シマネトリコ
成長も早く、庭木としての育てやすさから人気のシンボルツリーです。生命力も高く少々の剪定ではびくともしません。しかし、その生命力の高さから、枝や葉は勢いよく育ちます。
そのため、剪定するだけでも、枝木や葉の処理にかかる労力は大変なものでしょう。また、シマネトリコのサイズは大きくなりやすいため、脚立などを使用せず普通に立ったままでの剪定はよりむずかしいものとなってしまいます。
〇シラカバ
白い幹の外見が特徴的で、おしゃれな雰囲気を作り出せることからシンボルツリーとしても人気の木です。しかし、シラカバには天敵の害虫がいることも知っておいたほうがよいでしょう。テッポウムシといわれる、シラカバを好物とした害虫がいます。
テッポウムシは、シラカバを食料とし、木の内部や表面を食べてしまうのです。テッポウムシの被害にあったシラカバは、枯れるだけでなく、倒木の危険性も十分に考えられます。
シラカバを害虫から守るには、日ごろのメンテナンスが大切なのです。そのため、害虫対策なしでは、シラカバの健康状態を維持するのはむずかしいでしょう。また、シラカバの全長は、一般的な家の2階をも越してしまうほど大きくなることもあり、剪定は決して簡単なものではありません。
一番大事なのは残したいかどうか
庭木を育てるうえで一番大事なのは、伐採するのか、残したいかでしょう。庭木には、強い風から家屋を守ってくれることや外からの目隠しにもなるなど、メリットも存在します。
また、庭木によっては季節の変わり目を楽しんだり、おしゃれを楽しむこともできるでしょう。しかし、庭木にトラブルが発生している場合は、伐採の決断が必要となるかもしれません。このような庭木をそのままに放置しておくことは、大変なリスクをともなうのです。
トラブルを抱えているなら伐採を決断しよう
大きくなりすぎた庭木は自分の敷地内だけでなく、隣の家の敷地にまで影響を与えてしまうことがあります。たとえば、庭木の根が次のような被害を出すおそれもあるのです。
地中から伸びた根が、隣の庭に侵入し地面に凹凸をつくってしまったり、建物の下に根が入り込んだりする場合があります。こうなると、地面の凸凹だけでなく、家の傾きにつながる場合もあるでしょう。
また、庭木には虫も寄ってくることもありますので、虫が苦手な方にとっては決して無視できる問題ではありません。そのうえ、庭木が病気にかかれば、害虫発生のリスクも高まってしまいます。
周囲への影響を考え、いざ伐採をおこなおうにも大きく育ってしまった庭木は、手に負えないかもしれません。その場合は、業者に相談してみてはいかがでしょうか。業者であれば、自分で解決できそうにない庭木への対応だけでなく、さまざまなトラブルを未然に防いでくれることでしょう。
【警告】剪定を急ぐと逆効果!じっくり小さくしていこう
大きくなりすぎた庭木は、早くどうにかしたいですよね。しかし、剪定は適切な方法でおこなわなければ、逆効果になることがあるので注意が必要です。
間違えた枝切りをおこなってしまった場合、予想外に枝や葉が増えることがあります。そうならないためにも、庭木はあせらずに小さくすることが大切でしょう。また、庭木には剪定の時期やコンパクトに維持する方法もありますので紹介していきます。
剪定時期

庭木の剪定の時期として、夏季と冬季があり、このふたつが一般的な剪定時期となります。冬季の剪定は、庭木が成長する春ごろを見越して、大部分の枝や葉を減らす作業が多くおこなわれます。
一方、夏に剪定をおこなう場合は、枝を短くすることで台風など強い風によって枝が折れることを防ぐ目的のほか、枝木や葉を剪定し、庭木のバランスを調整することが目的となっています。
剪定で高さを抑える方法
庭木の剪定には高さを抑える方法として芯止めとよばれる剪定方法があります。芯止めとは、庭木の中心部分に位置する主枝を取り除くことをいい、主枝を取り除くことで縦方向に庭木が伸びることを防ぐことができるのです。
そのため、木の高さは抑えられ、庭木として適切な高さで育てることが可能となります。注意点は、芯止めをおこなった庭木は、縦以外に新芽や枝が伸びやすくなるという特徴があるということです。庭木として全体のバランスを考えた場合は、縦だけでなく横に伸びる枝や葉の適切な剪定も忘れないようにしましょう。
枝切りを急ぐと葉が大量に生えてくる!
庭木の剪定はやり方を間違えると葉が大量に生えてしまうおそれがあります。木の生命力は非常に高く、剪定をおこなっても新しい枝を生やそうとする力が働きます。
そのため、適切なタイミングではない枝切をおこなってしまった場合、切った場所から細い枝が大量に生えてくる場合があるのです。結果として、枝から大量の葉を生み出してしまうことになるでしょう。
庭木をコンパクトに維持する方法
庭木をコンパクトに維持するには、切り返し(切り戻し)といわれる剪定方法が有効です。切り返しとは、ダメージのある枝を切り落として枝の勢いを回復させる方法のことをいいます。切り返しを施すことで、結果として庭木全体の縮小につながっていきます。
また、切り落とした枝からは新しい枝が生えてくることにくわえ、残された枝や芽は成長が盛んになります。そのため、切り返しは大きく育てたい果実や花がある場合にも、有効な剪定方法となっています。
庭木の相談ごとはプロに
庭木の剪定は、木の種類や特徴をきちんと理解しておく必要があります。木によって切り落とすべき箇所が違うため、主枝を切ってしまい予定より庭木が育たないことも考えられるのです。
また、庭木に果実や花を咲かせたい場合など、適切な剪定方法なしには、うまく成長できないこともあるでしょう。ほかにも、大きくなりすぎた庭木は手に負えなくなるおそれがありますので注意が必要です。
庭木のことで不安に感じることがある場合は、一度、業者に相談してみることをおすすめします。業者であれば、適切な剪定方法で庭木の樹形を維持しやすくしてくれるため、理想のシンボルツリーを育てることができるでしょう。
庭木のメンテナンスをラクにする方法
庭木のメンテナンスは楽なものではありません。理想のサイズで庭木を維持するには、適切な方法で剪定をおこなっていくことが大切でしょう。また、間違えた方法で剪定をおこなうと、庭木が大きくなりすぎたり枯れてしまったりなどのリスクがあるので注意が必要です。
庭木に必要なメンテナンス

大きくなりすぎた庭木はそのまま放置しておくと、庭の景観を損ねるだけでなく、害虫が発生することもあります。そのため、普段からのお手入れが大切です。
剪定と一言でいってもさまざまな方法や目的があります。たとえば、芽摘みは木にできる芽を手作業で摘み取っていく作業のことをいいます。このように剪定には、庭木の形を整える目的だけでなく木枝の成長をおだやかにする目的もあるのです。
ほかにも、刈り込みや切り戻しでは、庭木の景観を整えることができます。注意点は、適切な剪定方法でなければ、不要な枝や葉が逆に増えてしまうおそれがあることです。
また、庭木自体を元気に育てるために、透かし剪定という増えすぎた枝を切る作業などがあります。このように、剪定作業は、適切な時期におこなう必要があるうえ、間違った時期におこなってしまった場合、庭木が枯れるおそれや大きくなりすぎることもあるので注意が必要でしょう。
【ラクする方法1】メンテナンスが楽な木に植え替える
庭木のメンテナンスを楽にする方法として、管理が楽な木に植え替える方法もあります。低木といわれる比較的小さなサイズで育てることが可能な常緑樹などがおすすめです。常緑樹は、景観を楽しめるだけでなく、落葉樹と違い、葉が落ちにくいという特徴ももっています。
【ラクする方法2】木の本数を減らす
大きくなりすぎた庭木の処分は、自分では手に負えないということになりかねません。そこで、庭木の本数を減らすことでお手入れにかかる労力を減らす方法があります。自分できちんと管理できる庭木の量であれば、普段のメンテナンスも楽になるかもしれません。
ただし、本数を減らすには伐採をおこなう必要があり、すでに大きくなってしまった庭木や広い箇所に根が生えてしまっている場合はむずかしい作業となります。
残す木、伐採する木の選び方がむずかしい…そんな場合は
お家のシンボルツリーとして、お庭の景観を守る庭木をできれば伐採せずにそのまま育てたいという方も多いと思います。しかし、大きくなりすぎるおそれがある木やすでに害虫被害がでている庭木もあるかもしれません。
害虫被害だけでなく、大きくなりすぎた庭木は周囲にさまざまな影響を与えてしまいます。そのため、リスクを避けるには残しておいても大丈夫な木と、伐採しておいたほうがよい木を選ぶ必要があるでしょう。しかし判断を自分でおこなうことはむずかしいかもしれません。
また、庭木の成長を予想することはとてもむずかしいとされています。業者であれば、適切な知識と技術で、残す木と伐採する木を選び、お庭の木を伐採してくれるでしょう。
まずは、プロの目で現地を調査してもらってはいかがでしょうか。弊社では、現地調査は無料でおこなっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、24時間365日お電話を受け付けております。お庭の状況に合わせ、適切な業者をお客さまにサポートすることができます。

庭木処分は自分でやると、とても大変な作業です。そのため、庭の不要な木を処分したいという場合は、なるべく業者に庭木処分を依頼することをおすすめします。庭木処分をできる業者をお探しの際は、弊社の相談窓口にお電話ください。
このコラムでは、パターン別の庭木処分の方法についてご紹介していきます。また、業者に庭木処分を依頼した場合の費用相場などについても解説していくので、弊社サービスをご利用する際の参考にしてみてください。
生えている庭木を処分する方法
「庭に不要な木が生えていて処分をしたい」という場合は「伐採」をおこないましょう。伐採とは、ノコギリやチェーンソー、斧などを利用し、木を根元から切り倒す作業のことです。
ここでは、伐採に必要な道具や伐採の手順などについてご紹介していきます。また、木を安全に切るために重要な「受け口」「追い口」「ツル」についても解説するので、自分で庭木処分をする際の参考にしてみてください。
伐採に必要な道具

- ノコギリ/チェーンソー/斧:木を切るために使います。
- ロープ:木を倒す方向をコントロールするために使います。
- 楔(クサビ):追い口に打ち込み、木を倒す際に使います。
- ハンマー:楔を追い口に打ち込むために使います。
【チェーンソーで伐採をする場合】
チェーンソーを利用する際は、保護ゴーグルや作業服、安全靴や手袋などを身につけてケガを予防するようにしましょう。また、チェーンソーはものによってはかなりの騒音が発生します。騒音から耳を保護するためにも必要に応じてイヤーマフを用意したり、静音モデルのチェーンソーを利用したりして対策しましょう。
伐採の手順
- 木を切り倒す方向を決める。
周囲を見渡して、木が建物や道路などに倒れ込まない方向を見定めましょう。
- 木を倒す方向に向かってロープを張る。
- 木を倒す方向側に受け口をつくる。
- 受け口の反対に追い口をつくる。
安全に木を伐採するためにはツルを残す必要があるため、追い口を深く作りすぎないように注意しましょう。
- 木が倒れるまで追い口に楔を打ち込む。
安全な伐採をするためには「受け口」「追い口」「ツル」を意識しましょう!
木を伐採する際に、幹を直線的に切ろうとするとノコギリやチェーンソー、斧などの刃が切り口に挟まったり、木が想定外の方向に倒れたりする危険性があります。このよう事態を防ぐためにも、次の3点を意識して木の伐採をおこなうようにしましょう。
・受け口
木を倒す方向側につくる、くの字状の切り口です。切り口の深さは幹の直径の約1/3ほど、角度は30~45度が目安です。
・追い口
受け口の反対側につくる、直線状の切り口です。受け口の高さの2/3ほどの位置につくりましょう。切り口の深さは、幹の直径1/4~1/3ほどが目安です。
・ツル
受け口と追い口の間にある幹のことです。木を狙った方向に倒すために必要です。受け口や追い口を深く作りすぎると、ツルがなくなって狙った方向へ木を倒せなくなるおそれがあるため注意しましょう。
庭木を伐採した後に残った根株を処分する方法
木の伐採後は、木の根株が残った状態になります。完全に庭木処分をするためは、伐採のあとに「抜根」をおこないましょう。抜根とは、伐採後に残った根株を引き抜く作業のことです。ここでは、抜根に必要な道具や抜根の手順などについてご紹介していきます。
抜根に必要な道具

- シャベル:根株の周りの土を掘り返すために使います。大きいものと小さいものの両方を用意しておきましょう。
- 鍬:地中の邪魔な石を掘り返すために使います。
- ノコギリ/斧:根っこを切断し、根株を引き抜きやすくするために使います。
抜根の手順
1.シャベルで根株の周辺の土を掘り返す。地中の石は鍬で取り除きましょう。
2.ノコギリや斧で地中の根を切断する。
3.根株の下にスコップを差し込み、テコの原理で浮かして引き抜く。
伐採した庭木や抜根した根株を処分する方法
ここでは、伐採や抜根などの庭木処分作業をしたあとに発生するゴミ(幹や根株など)を処分する方法についてご紹介していきます。
・ゴミとしてだす
 自治体ごとに異なりますが、幹や根株は燃えるゴミまたは粗大ゴミとしてだせることがあります。しかし、ゴミとしてだせる幹や根株は、自治体のルールで定められた規定サイズ以下のものだけであることがほとんどです。幹や根株のサイズ次第ではゴミとして処分できないケースもあるため、必ず自治体のゴミ捨てルールを確認しましょう。
自治体ごとに異なりますが、幹や根株は燃えるゴミまたは粗大ゴミとしてだせることがあります。しかし、ゴミとしてだせる幹や根株は、自治体のルールで定められた規定サイズ以下のものだけであることがほとんどです。幹や根株のサイズ次第ではゴミとして処分できないケースもあるため、必ず自治体のゴミ捨てルールを確認しましょう。
・業者に回収してもらう
庭木処分作業後の幹や根株を回収してくれる業者には、廃品回収業者があります。廃品業者とは、有料で不用品を回収してくれる業者のことです。ゴミにだす方法と比べて処分費は高くなりますが、大きい幹や根株でも処分してくれます。
また、自宅まで不用品を引き取りに来てくれるため、自分でゴミ収集所まで幹や根株を運ぶ手間が省けます。業者によって回収料金は異なるため、利用前にしっかりと確認をとりましょう。
伐採業者に依頼して庭木処分をする方法。業者に依頼する際の相場はいくら?
ここまで、庭木処分の方法についてご紹介していきました。実際にこれらの作業をすべて自分でやるとなると、かなりの重労働になります。また、庭木の大きさによっては重機を使わないとまともに庭木処分をおこなえないケースもあります。
「庭木が大きすぎで自分では処理できない」「なるべく手間をかけずに庭木処分をしたい」という方は伐採業者に依頼してみてはいかがでしょうか。伐採業者であれば、伐採~ゴミ処理までの庭木処分作業を一括で依頼することも可能です。
ここでは、伐採業者に庭木処分を依頼した際の相場についてご紹介していきます。伐採業者に作業を依頼する際の参考にしてみてください。
【伐採の費用相場】
 伐採の費用は「木の高さ」によって変動するケースが多いです。
伐採の費用は「木の高さ」によって変動するケースが多いです。
| 高さ3m未満 |
5,000円前後 |
| 高さ3~5m未満 |
15,000円前後 |
| 高さ5~7m未満 |
30,000円前後 |
【抜根の費用相場】
抜根の費用は「幹回り(幹の太さ)」によって変動するケースが多いです。
| 幹回り30cm未満 |
5,000円前後 |
| 幹回り30~40cm未満 |
10,000円前後 |
| 幹回り41~50cm未満 |
20,000円前後 |
ゴミの処分費は業者によって大きく料金設定が異なるため、事前に確認をとるようにしましょう。また、木の大きさ次第では重機がないと庭木処分をおこないケースがあります。
重機が必要になるとその分庭木処分の費用も高くなります。料金トラブルを避けるためにも、なるべく現地調査をおこなったり見積りをとってくれたりする業者を選ぶことをおすすめします。
庭木処分をしてくれる業者をお探しの際は弊社にご相談ください。弊社では、作業前に見積り調査をおこない、分かりやすい見積りをだす安心して利用できる業者をご紹介しています。相談窓口は24時間365日いつでもご利用できるため、お気軽にお電話ください。





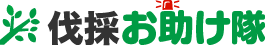
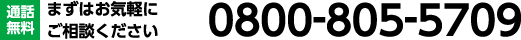















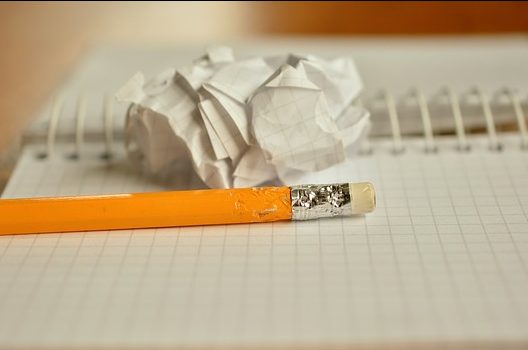























 自治体ごとに異なりますが、幹や根株は燃えるゴミまたは粗大ゴミとしてだせることがあります。しかし、ゴミとしてだせる幹や根株は、自治体のルールで定められた規定サイズ以下のものだけであることがほとんどです。幹や根株のサイズ次第ではゴミとして処分できないケースもあるため、必ず自治体のゴミ捨てルールを確認しましょう。
自治体ごとに異なりますが、幹や根株は燃えるゴミまたは粗大ゴミとしてだせることがあります。しかし、ゴミとしてだせる幹や根株は、自治体のルールで定められた規定サイズ以下のものだけであることがほとんどです。幹や根株のサイズ次第ではゴミとして処分できないケースもあるため、必ず自治体のゴミ捨てルールを確認しましょう。 伐採の費用は「木の高さ」によって変動するケースが多いです。
伐採の費用は「木の高さ」によって変動するケースが多いです。